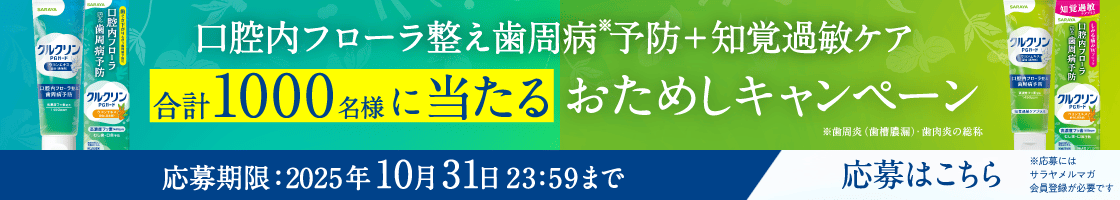歯周病の原因は細菌にある!主な症状や自分でできる予防策

歯周病は、日本人が歯を失う原因の第1位です。
これは公益財団法人8020推進財団が2018年、全国約2,500の歯科医院を対象に行った「永久歯の抜歯原因調査」の結果で、信頼性の高いデータです。
このように、日本人の歯の健康に大きな影響を与える歯周病ですが、「細菌の感染が原因」ということをご存じでしょうか?実は、歯周病は「人類に最もまん延している感染症」としてギネスブックにも掲載されました。
そこで今回は歯周病の発症原因である細菌に注目し、歯周病のメカニズムや症状、予防のためのセルフケアなどを解説していきます。
その前に、歯周病について簡単に説明しておきましょう。
歯周病は、歯と歯肉の隙間(ポケット)にたまったプラークを餌に増えた歯周病菌が、歯を支える結合組織や骨(歯槽骨:歯の周りの骨)を溶かし、歯をグラグラにしてしまう病気です。
歯肉で細菌が繁殖すると、まずは炎症を引き起こします。この炎症を「歯肉炎」、結合組織や歯槽骨(歯周組織)まで炎症が広がったものを「歯周炎」と呼びます。重度の歯周炎で歯茎から膿が出る状態が歯槽膿漏(しそうのうろう)です。
近年、歯周病は、動脈硬化や心血管疾患(脳梗塞や狭心症、心筋梗塞など)、糖尿病などの全身疾患を引き起こすリスクを高める危険因子として注目されています。
歯周病についてさらに詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
- 合わせて読みたい
- 歯周病になぜなるの?直接的な原因や進行したときの症状、予防方法
歯周病を引き起こす原因は細菌
歯周病を引き起こす直接的な原因は「歯周病菌」と呼ばれる細菌です。
歯周病菌とは、一つの菌だけを指す名称ではありません。「歯周病を引き起こす菌」という意味で使われ、数十種類の細菌が含まれます。新たに見つかる菌も多く、歯周病のメカニズムはまだ十分に解明されていません。
代表的な歯周病菌には、次の菌があります。
歯周病菌の種類
| ポルフィロモナス・ジンジバリス (Porphyromonas gingivalis) |
・略称は「P.g.菌」
・嫌気性のグラム陰性桿菌
・歯ブラシでは取れにくいバイオフィルムを作る
・歯槽骨を溶かす毒素を産生する
・慢性歯周病の患者からよく検出される |
| アグリゲイティバクター・アクチノミセテムコミタンス
(Aggregatibacter actinomycetemcomitans)
|
・昔は「アクチノバチルス・アクチノミセテムコミタンス」と呼ばれていた
・略称は「A.a.菌」
・嫌気性のグラム陰性桿菌
・進行の早い歯周炎の患者からよく検出される |
| プレボテーラ・インターメディア
(Prevotella intermedia) |
・略称は「P.i.菌」
・嫌気性のグラム陰性桿菌
・妊娠性歯肉炎の患者からよく検出される |
| タネレラ・フォーサイシア
(Tannerella forsythia) |
・略称は「T.f.菌」
・嫌気性のグラム陰性菌
・重度の歯周病患者からよく検出される |
| トレポネーマ・デンティコラ
(Treponema denticola) |
・略称は「T.d.菌」
・スピロヘータ (細長いらせん状の嫌気性グラム陰性菌)
・強い運動性があり歯茎から血管に入り込んで全身を巡る |
グラム陰性菌、グラム陰性桿菌、スピロヘータなどは菌の種類の名前です。「嫌気性」とは「空気を嫌う」という意味で、これらの細菌は生育に酸素を必要としない特性をもちます 。歯周病菌とされる細菌には、歯周病菌の多くは嫌気性なので、歯茎の奥深く(空気が少ない場所)を好みます。そのため、ポケットが深いほど歯周病菌が多く生息します。
歯周病菌によって歯周病が引き起こされるメカニズム
歯磨きが十分でないと、歯と歯茎の境目にある溝にプラーク(歯垢)が溜まります。プラークは、細菌とその代謝物のかたまりです。
プラーク中の歯周病菌の毒素が歯肉に炎症を引き起こし、溝が深くなって歯周ポケットが作られます。歯周ポケットができるとプラークが溜まりやすくなり、ポケットの内部で細菌が増殖し、さらに多くの毒素が産生されます。
その結果、炎症が結合組織や歯槽骨などの歯周組織にも広がり、骨を溶かし始めて中等度以上の歯周病になるのです。
歯周病になる流れ
| 0)健康な状態 | 1)軽度歯周病 | 2)中度歯周病 | 3)重度歯周病 |
| 歯周ポケットが形成され歯肉が腫れている | ポケットがさらに深くなり、歯茎が痩せ歯槽骨も溶ける | 周囲組織の破壊が進み、歯がぐらぐらする |
- 合わせて読みたい
- 歯周病の原因はプラークにある?歯垢が溜まる原因や予防方法
歯周病の原因となる細菌はどこから来る?
歯周病菌がどこから来たかは分かっていませんが、太古の昔から人類に感染していたようで、すでに6万年前のネアンデルタール人の化石から歯周病菌が見つかっています。
歯周病菌が人から人に感染する原因は「唾液」です。例えば、食べ物や飲み物の共有や、キスなどを通じ、歯周病菌が含まれた唾液が移動することで感染を媒介するようです。
ただし、一説には現代人の約8割がもつとされるほど歯周病菌の感染は広がっており、口腔内の常在菌(※)に近い存在になっているとも言います。そのため、口腔内にすでに生息していることを前提に「歯周病菌が悪さをしない」ようにするのがよいかもしれません。
※常在菌:人間の体内や皮膚に常に生息し、共生している微生物のこと。
「歯周病菌が悪さをしない」ようにするための重要な対策の一つは「清掃」です。口の中を毎日の歯磨きなどできれいにし、歯周病菌の数を減らすと、 病原性の低下に伴い、歯周病リスクも低下します。歯周病菌は数が少ないと大人しいですが、数が増えると活動が活発になり、病原性が高くなるので注意してください。むし歯(う蝕)対策も同様で、清掃により原因菌の数を減らすことが大切です。
この次に大切なこととして専門家による定期的なクリーニングが挙げられます。定期的に(数ヶ月から半年に一回程度)歯科医院で清掃を受けることで、日々のケアでは取り切れない歯周病菌を減らすことができます。
加えて、口腔内フローラを整えることも重要です。口腔内フローラとは、口の中に生息する約700種類・1000億個以上もの細菌たちが作る「独自の世界」をいいます。細菌たちは「口腔内フローラ」という世界の中で互いに影響し合って生息し、口の中の環境維持に役立っているのです。
「口腔内フローラ」という世界では、菌のバランスが重要になります。清掃が不十分だったり栄養バランスが偏っていたりなどの様々な理由で特定の菌だけが増えると、「口腔内フローラ」のバランスが崩れ、口の中の健康状態に様々な悪影響をもたらすのです。
口腔内フローラが乱れると、歯周病菌の活動も活発になります。口腔内フローラは、歯周病予防を考えるうえで重要な視点です。
歯周病の原因となる細菌が増えすぎないようにするには?
歯周病予防のためには、口腔内フローラを整え、口の中の歯周病菌を増やしすぎないようにすることが大切です。
歯周病菌の多くはプラーク(歯垢)の中で繁殖するため、歯の表面や歯と歯茎の境目の溝、歯と歯の間のプラークを除去して減らす必要があります。では、具体的にどのようなケアを行えばよいのでしょうか?
毎日の正しい歯磨き
少なくとも1日2回以上、歯磨きをしましょう。特に夜寝る前は時間をかけて丁寧に磨いてください。磨き方のポイントは次の通りです。
・歯ブラシの選び方
歯肉の腫れが気にならない方は「ふつう」、腫れや知覚過敏が気になる方は「やわらかめ」を使いましょう。「かため」は歯や歯肉を傷つけることが多いのでおすすめしません。コンパクトなヘッドは隅々まで磨きやすいという利点があります。毛先が細くなっていたり、ギザギザしていたりするタイプではなく、シンプルな歯ブラシを選びましょう。
・歯ブラシの交換の目安
1ヶ月に1回を目安にしましょう。見た目が毛先が開いてなくても1ヶ月もすると毛先の弾力が落ちて清掃効果が激減します。すぐに毛先が開いてしまう人は歯磨きするときの力が強すぎるかもしれません。
・歯ブラシの持ち方
余分な力が入らないよう、ペングリップを基本にします。鉛筆のような持ち方です。
▼磨き方
歯ブラシの毛先を歯に直角に軽く当てて小刻みに動かすスクラビング法、毛先を歯と歯茎の境目に45度の角度で軽く当てて弱い力で横に振動させるバス法など様々な方法を駆使し、磨き残しのないようにプラークを除去していきます。歯茎は傷つきやすいので優しい力でブラッシングしましょう。ゴシゴシと強く磨かないようにしてください。
▼歯磨きの時間
プラークは粘着性が高いため、少し磨いただけでは落ちません。1日1回は5分以上かけ、1か所当たり10~20回くらい小刻みに歯ブラシを動かし、隅々まで丁寧に磨きましょう。
正しい歯磨き方法は、次の記事で詳しく解説しています。
- 合わせて読みたい
- プラークをきちんとケアする歯ブラシのやり方はこちらから
定期的な歯間ケア
歯と歯の間(歯間)のプラークもデンタルフロスや歯間ブラシなどで定期的に取り除きます。
デンタルフロスは、ホルダーにフロスが取り付けられたホルダータイプ(糸ようじ)とロールタイプ(糸巻きタイプ)がありますが、慣れないうちはホルダータイプが使いやすいでしょう。鏡を見ながらゆっくりと歯間に糸を入れ、上下に動かしてプラークや汚れを除去します。
歯茎を傷つけないように気を付けましょう。出血にも注意が必要です。
歯間の隙間が広い場合は、デンタルフロスよりも歯間ブラシの方がプラークを除去しやすいです。
デンタルフロスの使い方は、次の記事で詳しく解説しています。
- 合わせて読みたい
- デンタルフロスのやり方について詳しくはこちら
規則的な生活習慣
偏食は歯茎の健康に悪影響を与えます。栄養のバランスの取れた食生活を心がけましょう。
またよく噛んで食べることも重要です。食べ物をしっかり噛むと、歯に付着したプラークが取り除かれます。特に食物繊維の豊富な食べ物は、噛むことで歯を清掃する役割も果たします。例えば、ごぼう、にんじん、レタス、セロリには高い清掃効果があります。
喫煙者は喫煙を控えることも重要です。たばこは血流を悪くし、歯茎の健康に阻害します。
歯科医院での定期検診
食べカスは食後数時間でプラークになり、その後、1日ほどで石灰化が始まり、1週間もすると固い「歯石」になります。歯石そのものが毒素の塊です。たくさんたまると周囲の歯槽骨が破壊され歯肉も痩せてしまいます。歯石は自力での除去が難しいため、たくさんたまる前に歯科医院でリセットしましょう。定期的な歯科検診、歯のクリーニングなども重要です。
口腔内フローラを整えるアイテムを取り入れる
口腔内フローラをつくる細菌は大きく「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の3つに分類されます。善玉菌は人体によい影響を与える菌、悪玉菌は悪い影響を与える菌、日和見菌(ひよりみきん)は善玉菌・悪玉菌の一方が優勢になると、優勢な方に加担するどっちつかずの菌というイメージです。
先ほど口腔内フローラのバランスが重要と述べましたが、具体的には善玉菌・悪玉菌・日和見菌が拮抗してバランスが保たれていることが重要になります。
歯ブラシや洗口剤には、悪玉菌だけでなく善玉菌や日和見菌まで殺菌してしまうものがあり、かえって口腔内の環境を乱すケースがあるため、口腔内フローラを整えて悪玉菌だけを抑制できるオーラルケアアイテムを取り入れることがおすすめです。
歯周病の予防には「細菌」に注目しよう
歯周病は、むし歯と同様に細菌が原因です。
しかし、歯周病菌が口の中に生息するからといって必ず歯周病になるわけではありません。不十分な歯磨きや歯間ケアによるプラークの蓄積、抵抗力の低下、口腔内フローラの乱れなどの要因が絡み合い、歯周病菌の毒素が歯肉に炎症を引き起こし、歯茎の組織を溶かし始めるのです。
歯周病の予防は、毎日の歯磨きを基本とした口腔ケアが大切です。口の中を清潔に保ち、口腔内細菌のバランスを整えて、お口と歯茎の健康を守りましょう。
- 合わせて読みたい
- 「口腔内フローラ」を知っていますか?お口の健康が全身の健康に

監修:牧浦 倫子
大学を卒業後、口腔外科の医局に3年間在籍、その後数カ所の関連病院に出向。病院では
「抗血栓療法中患者の抜歯の管理」「糖尿病患者さんの口腔ケア」などに取り組む。病院退職後、父の診療所を継承、現在に至る。地域の医科と連携して患者さんのサポート、口腔機能向上に努める。最近は歯科の観点からの栄養指導も取り組み始めている。