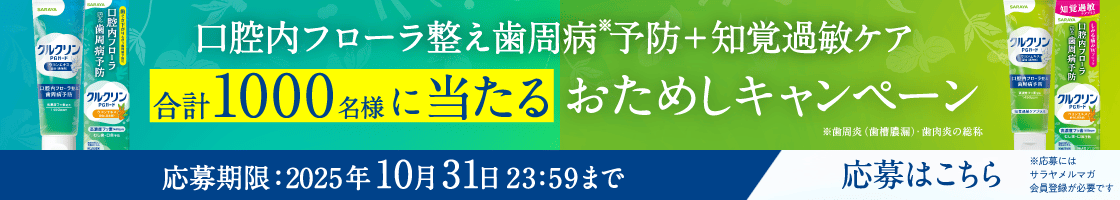歯周病の原因はプラークにある?歯垢が溜まる原因や予防方法

ミドルエイジ以上の方はそろそろ歯周病が心配になっていませんか?
20代・30代の方、「歯周病は自分にはまだ関係ない」と思っていませんか?
実は歯周病の初期症状である歯肉炎は、若い層や子どもにも多く見られます。
歯周病が進むと、回復に長い時間がかかり、進行すると歯を失うだけでなく、口腔内の細菌が血管や、唾液を介し全身の健康に影響を及ぼすこともあるのです。ぜひ、歯周病の危険に気づいた今から、対策を始めましょう。
歯周病の最大の原因は歯や歯周ポケットに付着した「プラーク」です。
プラークは、単なる食べカスではなく「細菌のかたまり」で、歯垢(しこう)とも呼ばれます。「デンタルプラーク(dental plaque)」の略称です。
プラークは乳白色で歯に似た色調をしており、時間の経過とともに黄色く変化して最後は石灰化して硬い「歯石」になります。
プラーク中には、むし歯菌や歯周病菌を含む、多種多様な菌が大量に含まれています。むし歯や歯周病の原因になるだけでなく、放置すると唾液を介して肺炎を引き起こしたり、全身のさまざまな病気の悪化に関与したりと、様々な健康リスクがあります。
本記事では、プラークの蓄積を予防し、歯周病を防ぐ方法や、口の中の細菌をコントロールする重要性を解説します。
プラークが「歯周病」の原因となるメカニズム
冒頭で、プラークは歯周病の最大の原因であると説明しました。では、プラークはどのように歯周病を引き起こすのでしょうか。プラークと歯周病の関係を解説してきます。
歯周病とは?
まず、「歯周病とは何か」を見ていきましょう。
歯周病とは、歯と歯茎(歯肉)の隙間(歯周ポケット)から侵入した細菌が、①歯肉に炎症を起こした状態(歯肉炎)、②それに加えて歯を支える骨(歯槽骨)を溶かしてグラグラにさせてしまう状態(歯周炎)の総称です。歯周病が進み歯肉から膿が出る状態を「歯槽膿漏(しそうのうろう)」とも呼びます。
プラークはどのように歯周病を引き起こす?
歯と歯肉の溝、歯と歯の間(歯間)には、食べ物のカスが残りやすく、歯磨きで落とし切れなかったカスに細菌が集まりプラークを作ります。プラークには1グラム当たり1000億もの細菌が含まれており、便に匹敵する濃度です。
プラークの細菌が出す毒素によって炎症を起こし、歯肉が腫れて赤くなる歯肉炎を引き起こします。
歯肉炎が悪化すると、歯と歯肉をくっつける歯根膜や歯周靱帯、歯槽骨、セメント質にまで炎症が広がります。これが歯周炎です。歯肉が赤く腫れるだけでなく、痛みや歯磨きの際に出血の症状が出るようになります。
歯根膜や歯周靱帯が炎症で破壊されてできた溝が「歯周ポケット」です。
歯周ポケットができると歯垢がさらに溜まりやすくなり、底の方では歯石化も進みます。
プラークが溜まって歯周病が進行するとどうなる?
プラークを残したままにすると、歯周病が起こるメカニズムを理解いただけたでしょうか。では、歯周病がさらに進行するとどうなるか、歯周組織以外にどのような悪影響をもたらすのかを解説します。
歯を失う
プラークや歯石が残る限り感染と炎症は進みます。歯周ポケットが広がり歯槽骨の破壊が進むと歯がぐらぐらするようになり、最後には歯を失います。
むし歯になりやすくなる
プラークには、むし歯菌も多く含まれます。むし歯菌は糖質を栄養素として乳酸菌を作り出し、その酸で歯の表面のエナメル質を溶かします。エナメル質が溶けて穴が開いた状態がむし歯です。
つまり、歯周病でできた歯周ポケットのプラークを放置すると、むし歯のリスクも高くなると言えるでしょう。
口臭の原因になる
一般的な口臭の原因は、口の中の細菌(口腔内細菌)です。細菌が食べカスや死んだ細胞のタンパク質を分解して臭気物質(ガス)を発生し、口臭につながります。
プラークには多数の細菌が存在し、臭気物質を発します。特に酸素を嫌う「嫌気性菌」が臭いの強いガスを発生させますが、プラークの内部や歯周ポケットの奥は嫌気性菌の活動に絶好の環境になっており、歯周病が進むほど口臭が発生しやすくなるのです。
別の病気を引き起こすことがある
口の中の細菌が唾液を介し気管支や肺に入り気管支炎や誤嚥性肺炎を引き起こすことが知られています。歯周病では特にリスクが高まるでしょう。
また最近は歯周病菌や炎症反応性物質が歯茎の血管を通じて全身を巡り、動脈硬化や心血管疾患(脳梗塞や狭心症、心筋梗塞など)、糖尿病などの全身疾患や、低体重児出産・早産などを引き起こすリスクを高めることがわかっています。
糖尿病は、歯周病を引き起こすリスクにもなるので血糖値のコントロールが重要です。このほか骨粗鬆症の人も歯周病になりやすくなります。
プラークが溜まる原因
では、プラークはなぜ溜まり、取れにくいのか、詳しく説明しましょう。
これまで解説してきたように、歯磨きで除去できなかった食べカスが歯と歯肉の溝、歯と歯の間に溜まり、細菌が繁殖してプラークになります。
プラークは時間が経つとネバネバしますが、これは細菌の排泄物がスライム状になったバイオフィルムです。バイオフィルムは、お風呂場のぬめりなどをイメージするとわかりやすいでしょう。
ネバネバには口の中にもともといた細菌だけでなく、外から呼吸や飲食などを通じて侵入してきた細菌も付着します。その結果、プラークはますます多種多様な菌のかたまりになり、増殖していきます。
お風呂場のぬめりが取れにくいように、ネバネバしたプラークはなかなか取れません。マウスウォッシュや洗口液だけでは除去できず、ブラッシングとフロスが必要です。
プラークは歯肉の高さより上の「歯肉縁上プラーク」と、歯周ポケット内の「歯肉縁下プラーク」に分けられます。後者は除去しにくく、長い時間が経つと唾液に含まれるカルシウムなどに反応して石灰化し、硬い歯石になるので注意が必要です。
歯石はセルフケアで除去するのは難しく、骨を溶かす細菌叢は、歯肉縁下に多く存在します。歯科医院での、歯科医師や歯科衛生士によるP M T C(professional mechanical tooth cleaning:専門的機械的歯面清掃)が効果的です。
歯石はザラザラしており、歯ブラシで除去する事は難しいため、さらに細菌が付着しやすくなり、新しいプラークができて層が厚くなるという悪循環に陥ってしまいます。
プラークを除去して歯周病を防ぐには
歯石になる前に、プラークを除去しましょう。プラークをゼロにすることは難しいですが、セルフケアでできるだけ減らすプラークコントロールが重要です。
プラークが付着しやすい甘い飲み物や、ガム(キシリトールは除く)やキャラメルなど糖質が含まれる粘着性の食べ物の摂食頻度を少なくすることや、1日2回以上を目安に歯ブラシとフロスをセットで行うことが重要です。
一回あたりの歯ブラシの時間は最低10分で、磨き残しがないように右上の奥歯の表側から磨き始めて左奥の奥歯まで磨き、左側の奥歯を折り返し地点として裏側を磨くようにすると効果的です。歯ブラシだけだと全体の50パーセントほどしか磨けておらず、フロスを必ず併用しましょう。
また、出先や歯ブラシがない際は食事後にグチュグチュうがいを30秒ほど行い、糖質などを口の中に溜めないようにすることも大切なことです。
適切にブラッシングする
1日に2回以上を目安に歯磨きをしましょう。柔らかめの歯ブラシを使い、歯と歯肉の境目を丁寧にブラッシングします。歯周ポケットがあれば歯ブラシの毛が届くように磨きましょう。歯並びが悪い場所も要チェックです。
ブラッシングの際は、歯茎が傷つかないよう、手のひらに歯ブラシを擦りつけ白く濁る程度の力を加えるように意識します。
歯茎の腫れや出血、むし歯、口臭などもトータルで防げる薬用ハミガキを使うと効率的なので、おすすめです。
歯と歯の間にもプラークが溜まりやすいため、デンタルフロスや歯間ブラシなどを使って除去します。1日1回から2日に1回程度でよいでしょう。
よく噛んで食べる
よく噛んで食べると、唾液が多く分泌されます。唾液には抗菌作用があり、口腔内の細菌を抑制してくれます。また、唾液によって食べカスや細菌を洗い流す作用も重要です。唾液を多く出すことで、プラークの形成を防ぎます。
加えて、食べ物を噛んで飲み込む行為自体にも、歯の汚れを取る作用があります。
バランスの良い食生活をする
食物繊維を多く含む食品は、咀嚼することで歯を磨いてきれいにする働きがあります。清掃性食品と呼ばれ、ニンジン、ゴボウ、レタス、セロリなどが代表格です。歯につきやすい粘着性の食品が中心になるとプラークができやすくなるため、清掃性食品などを取り入れながらバランス良く食べましょう。
また、プラークを作る細菌の多くは糖質をエサにしています。甘く粘着性のあるもの(ガム、キャラメル)は控えめにするのがよいでしょう。
歯の定期検診を受ける
セルフケアだけでなく、定期的に歯科医院などを受診して歯の検診やプラーク・歯石除去、むし歯治療を受けることも大切です。
歯や歯肉の状況をチェックしてもらうほか、毎日の歯磨きだけではどうしても残ってしまうプラーク、自分では取れない歯石などを除去してもらいましょう。3か月~半年に1回は検診とプラーク・歯石除去が必要とされていて、口腔内の状況によってはもっと多いペースで通院する必要があります。
歯周病治療は長い期間がかかるため、プラークコントロールで発症を防ぎましょう。
プラークコントロールと歯周病対策を効果的に進めたいなら
お口のセルフケアをより効果的に進めたいなら、口腔内環境も大切です。
毎日のブラッシング後、新たなプラークの形成を抑制し、プラークコントロールを十分なものにするためには、口腔内細菌のコントロールが重要になります。
口腔内細菌は完全に除去できませんし、必要なものです。
むし歯や歯周病を引き起こす悪い細菌(悪玉菌)ばかりではなく、口腔内の環境を保ったり病原体から口の中の粘膜を守ったりと、良い働きをする細菌(善玉菌)もいます。悪玉菌とされる細菌であっても、有益な役割があることもわかってきており、そのバランスが重要なのです。
たくさんの口腔内細菌が織り成す世界(=口腔内フローラ)の環境を整えれば、むし歯・歯周病・口臭を同時に抑制できます。
普段のハミガキから口腔内フローラのケアを意識したい方は、ハミガキ粉などのアイテムで取り入れてみることがおすすめです。
- 合わせて読みたい
- 泡立ちすぎず磨きやすい薬用ハミガキ「クルクリン」について詳しくはこちら

監修:鈴木 遼介
歯科医師として、都内の医科と歯科の連携クリニックで勤務し、患者様の要望に沿う一般診療やインプラント治療などを主に行っている。レノプロジェクト(株)の腎機能検査、Dental Prediction(株)パートナーであり、AR技術を活用し、より安心安全な歯科治療を目指している。