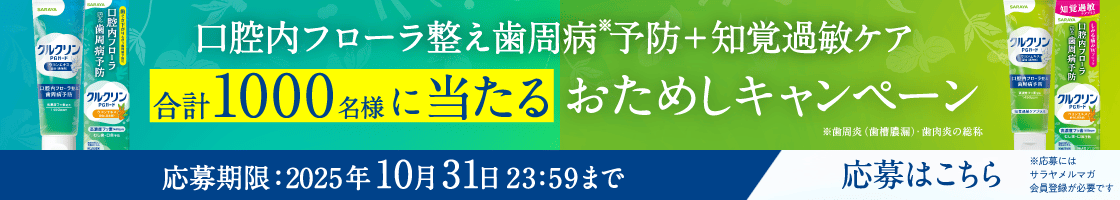歯茎が後退する原因は?歯肉が下がると起きやすい症状や予防方法

鏡を見て「歯茎が後退している」「歯が長い」などと感じたことはありませんか?
こういった歯茎の異変は下あごの前歯に起こりやすいため「歯茎が下がる」とも表現されますが、上あごの前歯や奥歯の歯茎でも起こります。
歯茎の後退は、40代以降のミドルエイジ以降の男女によく見られます。しかし、加齢だけが原因ではありません。20代・30代にも起こる可能性がある現象です。
今回は、歯茎が後退する原因や治療方法、予防法などを詳しく解説していきます。
「歯茎の後退」とは?
歯茎が後退する現象を、専門的には「歯肉退縮(しにくたいしゅく)」と呼びます。歯の周りの歯茎が減り、本来は歯茎に隠れている歯根が見えてしまう状態です。
歯はエナメル質という非常に硬い素材に覆われていますが、歯茎(歯肉)で隠れている歯の根っこ部分(歯根)にはエナメル質がなく象牙質がむき出しになるため、露出すると虫歯や知覚過敏(「しみる」「痛い」)、象牙質の色(茶色)が見える事などが生じます。
また、歯茎が後退すると、歯並びや咬合(かみ合わせ)の悪さ、歯と歯の隙間が目立ったり、口元の印象が変わったりするため、見た目の点でも悩ましい問題です。
歯茎の後退で起きやすい症状・見た目の問題をまとめると以下になります。
- 歯茎の後退で起きやすい症状・見た目の問題
- ・歯が長く見える
・歯と歯茎の境目に隙間を感じるようになる
・歯に食べ物が挟まりやすくなる
・歯に痛みが生じる・歯がしみる(知覚過敏)
・歯周病や虫歯になるリスクが高まる
・むき出しになった歯根部が着色しやすい
こうした問題に直面しないためにも、以後で解説する歯茎が後退する原因をチェックし、自力でできる予防法や対策を考えていきましょう。
歯茎が後退する原因
歯茎が後退する主な原因は、次の5つです。実際には複数の要因が絡み合って発生します。
①歯周病(歯肉炎・歯周炎)
歯周病は口腔内細菌の一つ、歯周病菌による感染症です。歯磨きや歯石除去などが不十分で、お口の中の清潔状態が悪いと、まず歯肉が炎症を起こして腫れ、次第に歯周組織(歯槽骨や結合組織など)に炎症が広がります。
歯肉や歯周組織が炎症で徐々に破壊されていき、歯茎が縮んでしまうというわけです。
- 合わせて読みたい
- 「歯周病の原因はプラークにある?歯垢がたまる原因や予防方法」
②加齢
加齢により歯肉は徐々に退縮し、歯根が露出しやすくなります。
③過度なブラッシング(オーバーブラッシング)
必要以上の力を入れて歯磨きをすると、ブラシの圧力や刺激によって歯茎の組織が傷つき、退縮しやすくなります。
④噛み合わせ
噛み合わせの悪い場所があると一部の歯へ極端に負担がかかり、歯茎が後退してしまうことがあります。
⑤生活習慣
歯ぎしり、歯の食いしばり、不十分な口腔ケア、喫煙、睡眠不足、ストレスなども歯茎の後退を引き起こします。
その他、遺伝的問題 、不適切な矯正治療、合わない入れ歯や被せ物、インプラント治療、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、妊娠などによるホルモンバランスの変化なども、歯茎の後退の要因です。
- 合わせて読みたい
- 「歯茎が痩せたかも?気になる症状の原因と進行させないためのケア」
後退した歯茎をもとに戻すことはできる?
残念ながら、一度後退した歯茎は基本的にもとに戻りません。歯茎の組織は自然に再生しないのです。
歯肉の移植など、外科手術による特別な治療法(遊離歯肉移植術、結合組織移植術、根面被覆術など)はありますが、高額な費用がかかってしまいます。
そのため、日々の口腔ケアや定期的な歯科検診と歯石除去により、進行を遅らせることが重要です。
また、前述の通り、歯茎の後退は複合的な要因で発生します。加齢や遺伝的な要因は防ぐことは難しいですが、口腔内の清潔を保ち、間違ったブラッシングを修正し、生活習慣を改善すれば、歯茎の後退の予防につながります。
歯茎の後退を防ぐ方法
歯茎の後退を防ぐには、毎日の適切な口腔ケアが重要です。歯周病菌や虫歯菌など口腔疾患の原因菌を多く含む歯垢(プラーク)を除去し、歯茎を健康な状態に保ちましょう。
①適切なブラッシング
歯磨きは1日2回以上を目安に行いましょう。歯ブラシの毛は柔らかく、頭の部分が薄くて小さいものを選び、力を入れ過ぎず、歯間や歯と歯茎の境目まで優しくきちんと磨きます。圧力のかけすぎは禁物。歯磨きの適切な力は150~200グラム程度で、これは歯ブラシの毛先が開かない程度の力です。
正しい方法の詳細は、次の記事を参考にしてください。
- 合わせて読みたい
- 歯茎の後退を防ぐ正しい歯ブラシの使い方はこちら
②歯間ケア
歯間ブラシやデンタルフロスなどを使い、歯と歯の間の汚れを取り除くことも重要です。歯間ケアの方法の詳細は次の記事をご覧ください。
- 合わせて読みたい
- デンタルフロスを使った気持ちいいお口ケアのやり方はこちら
③歯茎のマッサージ
歯茎の血行を促進して、歯茎の組織の健康を保ち、筋肉の緊張を和らげる方法です。
歯磨きの際に軽く歯ブラシで円運動や上下運動を行い、マッサージをします。清潔な指で歯茎に触れ、軽く押し上げる方法もあります。
歯茎の負担にならないよう、優しい力で時間は2分程度にとどめましょう。
④生活習慣の改善
歯茎の血行を悪化させないよう、禁煙、十分な睡眠、ストレス解消、栄養バランスの取れた食生活を実践しましょう。
歯茎の後退が気になるなら…
歯茎の後退がなぜ起こるか、後退すると歯の健康にどのような影響があるか、おわかりになりましたか?
歯茎の後退には加齢や遺伝など、自身では避けにくい要因もありますが、ご紹介した通りセルフケアで防げる要因も多くあります。特に大切なのは、毎日の口腔ケア。適切な歯磨きや歯間ケア、マッサージで歯茎の健康を守りましょう。

監修:鈴木 遼介
歯科医師として、都内の医科と歯科の連携クリニックで勤務し、患者様の要望に沿う一般診療やインプラント治療などを主に行っている。レノプロジェクト(株)の腎機能検査、Dental Prediction(株)パートナーであり、AR技術を活用し、より安心安全な歯科治療を目指している。