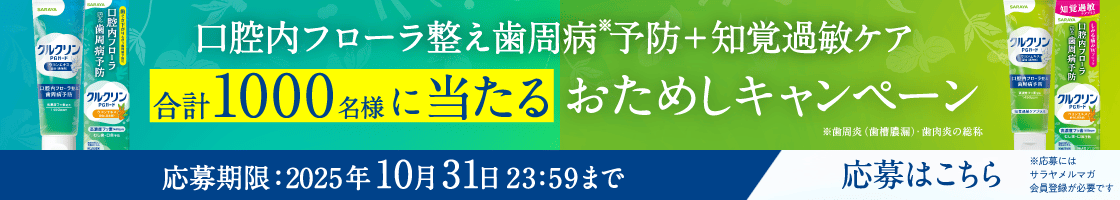歯茎の炎症の対処法は?歯医者に行くべき炎症の見分け方やケア方法

歯茎(歯肉)の炎症といえば、すぐに歯肉炎や歯周病をイメージするかもしれません。しかし、歯茎に炎症を起こす「お口の病気・トラブル」は、歯周炎や歯周病だけではありません。
なかには歯科医院で受診が必要な歯茎の炎症もあります。また、炎症の原因に全身の疾患が隠れているケースもあるのです。
今回の記事では、歯茎に炎症を引き起こす病気・トラブルの種類、受診すべき歯茎の状態、自分でできるホームケアのポイントを紹介します。
歯茎に起きる炎症の主な種類
歯茎に起きる炎症は大きく、①感染によるもの、②外傷や物理的な力によるもの、③ストレス・栄養不足によるものなどに分けられます。もちろん、原因は一つではなく、感染の背景にストレスや栄養不足、免疫の低下などが複合的に影響しているケースもあります。
では、歯茎に炎症を起こす代表的な病気・トラブルについて、それぞれ解説します。
歯肉炎
歯肉炎とは、歯茎(≒歯肉)に起こる炎症の総称ですが、一般的には歯と歯茎の間の溝に溜まった歯垢(プラーク)や歯石(※)に含まれる歯周病菌の感染による炎症をさします。歯周病菌による歯肉炎は「軽度の歯周病」です。
※歯垢(プラーク)は歯周病菌などの細菌のかたまり、歯石はプラークが石灰化したもの
このほか、糖尿病や白血病などの全身疾患、薬の副作用、ストレスによる免疫力低下の結果として生じる歯肉炎、妊娠による女性ホルモンの変化が引き起こす歯肉炎(妊娠性歯肉炎)などもあります。
- 歯肉炎の症状
- 初期は歯茎が赤みを帯びるほかは、自覚症状がない場合も多くあります。炎症が進むと次の症状が表れます。
・歯茎が赤く腫れる
・歯磨きの際に出血する
・歯茎にかゆみを感じることがある
さらに進むと、痛みや膿が生じたりしますが、その場合は中等度以上の歯周病である「歯周炎(歯槽膿漏)」とも呼ばれます。
歯周病
歯周病も一般的には歯周病菌の感染による炎症をいい、歯肉炎と歯周炎(歯槽膿漏)を含みます。歯肉炎が軽度の歯周病、歯周炎が中等度以上の歯周病です。
歯周炎は、歯周病菌の感染および炎症が歯肉を超えて歯根膜(歯周靱帯)や歯槽骨、セメント質などの歯周組織に広がった状態です。炎症により徐々に歯周組織が破壊され、放置すると重症化し、最終的には歯を失います。
歯周病は、次の流れで進行してきます。
①歯と歯茎の間の溝(歯周ポケット)に歯垢(プラーク)が溜まり歯肉に炎症が広がる
②歯と歯茎の結合組織が破壊されて歯周ポケットが深くなり、さらにプラークが溜まって炎症が拡大する
③歯肉を超えて歯周組織全体に炎症が広がり、組織の破壊が進む
④歯槽骨の破壊が進み、最終的には歯を失う
また、歯周病が進行すると、炎症によって生まれた毒性物質や細菌が血管に入り込んで全身に回り、より重い病気を引き起こすことがあります。糖尿病や動脈硬化、関節リウマチ、腎炎などが代表的です。
- 歯周病の症状
- ・歯茎が赤く腫れる
・歯茎が痛む(歯根の露出による知覚過敏)
・歯茎から出血する
・歯茎が下がる
・歯茎から膿が出る
・歯がぐらつく
・歯が抜ける
- 合わせて読みたい
- 歯周病の原因はプラークにある?歯垢が溜まる原因や予防方法
むし歯
むし歯(う蝕)は、むし歯菌が糖を分解する際に出す酸によって歯を溶かし、穴を開ける疾患です。エナメル質、象牙質が溶けて、歯の内部にある神経(歯髄)まで達すると、口の中に生息する細菌(口腔内細菌※)が出す毒素や口腔内細菌の感染により、歯髄が炎症を起こします。
※口腔内細菌は、歯周病菌やむし歯菌を含む700種類以上あり、口の中に1000億個ほど生息する
歯髄炎が進行すると、歯の根っこ(歯根)の尖った部分の血管や神経が通る穴から歯槽骨などの歯周組織に感染・炎症が広がり、歯周炎を起こします。これが「根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)」です。
歯茎の内部に膿が溜まり、歯茎が大きく腫れます。
- むし歯の症状
- ・歯に黒ずみがある
・歯に穴がある
・歯を噛みしめると痛い
・歯がしみる、歯と歯茎が痛い
・歯茎の一部が腫れる
・歯茎から膿が出る
歯根破折(しこんはせつ)
歯根破折は、歯の根元の部分(歯根)が割れる口腔内トラブルです。原因はさまざまですが噛む力が強いと起こりやすいとされています。むし歯治療で神経を抜いた歯が割れやすいとされています。
割れた部分から細菌の毒素が入ったり細菌感染を引き起こしたりして、根尖性歯周炎と似た流れで歯周炎を起こします。
- 歯根破折の症状
- ・神経を抜いた歯がムズムズする
・歯茎に白い”できもの”ができた
・歯茎の一部が腫れる
・歯と歯茎が痛い
・歯茎から膿が出る
智歯周囲炎(ちししゅういえん)
智歯周囲炎とは、親知らず(智歯)が原因で起こる歯肉・歯周組織の炎症です。
親知らずは一番奥にある奥歯(第三臼歯)のことで、歯肉に隠れて生えないままの人もいます。人間のあごは小さく進化してきたため、現代人の多くは親知らずが生える十分なスペースがありません。その結果、生えかけのままだったり斜めに倒れた状態で生えたりするため、歯に付着した細菌が繁殖してプラークが溜まりやすくなるのです。
親知らずは磨くのも難しく、汚れたままになりがちで、歯周病菌の感染が歯肉・歯周組織に広がり、智歯周囲炎を引き起こします。
- 智歯周囲炎の症状
- ・奥歯が腫れて痛む
・奥歯の歯茎から膿が出る
・口を開け閉めするときに違和感がある
・ほほが腫れる(放置するとあごから首まで炎症が広がり頬部蜂窩織炎になる)
・あごのリンパ節が腫れる
歯肉膿瘍
外傷や細菌感染をきっかけに歯肉内に膿が溜まる口腔内トラブルです。歯茎の内部が化膿した状態で、歯周病やむし歯、歯根破折、智歯周囲炎などでも起こります。
- 歯肉膿瘍の症状
- ・歯肉の一部が赤く腫れて盛り上がる
・普段から歯茎が痛み、出血する
・歯茎から膿が出る
・口が臭い
・発熱
・腫れた部分に黄白色の膿が透けて見えることもある
口内炎
口内炎とは、口腔内の粘膜にできる炎症の総称です。最も多いのが粘膜に2~10mmほどの潰瘍(えぐれた傷)ができるアフタ性口内炎です。歯肉にも生じます。
口内炎の原因はさまざまで、ストレスや疲労、睡眠不足、ビタミンBの不足のほか、傷への細菌感染、アレルギー、ウイルス感染などによっても起こります。
- 口内炎の症状
- ・食べ物や飲み物がしみる
・歯茎に口内炎ができると、腫れたり痛みが出たりする
- 歯茎の炎症への応急処置
- 歯茎につらい痛みや腫れが生じたら、早めに歯科医院に行くのが大切ですが、さまざまな事情ですぐに行けないときもあるでしょう。その場合は、次の応急処置がおすすめです。
1)うがいや歯磨きで口の中を清潔にする:やわらかい歯ブラシがよい
2)食べ物のカスが詰まっている場合は除去する
3)塩水でうがいをする
4)痛い部分を冷やす:タオルを巻いた保冷剤などをほほの上から当てる、氷を含む
5)痛み止めの市販薬を服用する
6)安静にして体力を回復する:睡眠も十分取る
歯茎の炎症の治し方
歯茎の炎症が歯肉炎や口内炎くらいなら歯磨きなどのホームケアで治ることが多いですが、炎症の原因を知るためにも一度、歯科医師に診てもらいましょう。単純な歯肉炎・口内炎でないかもしれませんし、歯垢(プラーク)除去や歯石除去などが必要かもしれません。歯磨きなどのセルフケアの指導もしてくれるでしょう。
「歯周病」「むし歯」「歯根破折」「智歯周囲炎」「歯肉膿瘍」は歯科医院で治療をするのが一般的です。「歯肉炎」「口内炎」の場合、多くは毎日のブラッシングや生活習慣の改善などのホームケアで対処します。
歯科医院でよく行われる治療法について簡単に説明します。なお一般的な解説であり、治療を受ける際は改めて歯科医師に詳細を聞いてください。
- 1)歯周病治療
歯科でのプラーク除去や歯石除去(プロケア)と、毎日のブラッシング・歯間ケア・歯肉マッサージなどのセルフケアを行います。禁煙、ストレスや睡眠不足の解消、ビタミンやミネラルの摂取などの生活習慣の改善も重要です。
なお、歯肉炎の段階からプラーク除去・歯石除去を行う予防歯科治療も重視されています。
2)むし歯治療
歯の溶けた部分を削って殺菌・消毒し詰め物をします。歯髄まで感染していれば歯髄を取り除いて洗浄し、患部に詰め物をします(根管治療)。根尖性歯周炎まで進んでいれば抜歯が必要になる場合も多いです。
3)歯根破折の治療
歯根へのヒビの入り方によって治療が異なります。ヒビが縦に深く入っていれば抜歯、ヒビが横に浅く入り歯根が残せるようならヒビより上部の歯を除去して被せ物をすることが多いです。
4)智歯周囲炎の治療
軽症の場合は腫れた部分を消毒・洗浄して抗菌薬を服用します。炎症が重度の場合は抗菌薬の点滴が必要で、入院するケースもあります。また、智歯周囲炎は繰り返すことも多いため、親知らずの抜歯も検討されるでしょう。
5)歯肉膿瘍
歯肉を切開して病巣から膿を出します。
歯茎の炎症の予防法
歯茎の炎症への対処では、歯磨きや歯間ケアなどのセルフケアが重要になります。日々のオーラルケアが変わらないと、歯科治療を行っても炎症の進行が止まらない、炎症を繰り返すなどの問題が生じるのです。
口腔内を清潔に保つ
歯茎の炎症を防ぐには、歯や歯間、歯周ポケットに歯垢(プラーク)が残らないようにする必要があります。歯ブラシで丁寧にブラシッシングし、口腔内の清潔を保つことが重要です。
ブラッシングで取り切れる汚れは70%程度とされています。歯と歯の間の汚れをデンタルフロスや歯間ブラシで除去しましょう。
ブラッシングの方法やデンタルフロスの使い方については次の記事をご覧ください。
- 合わせて読みたい
- デンタルフロスを使った気持ちいいお口ケアの方法&よくある疑問
- 合わせて読みたい
- 歯肉炎をケア・予防する歯ブラシの使い方|歯磨きで健康な口腔内に
口腔内フローラを整える
前述のとおり、口の中には700種類、1000億個もの細菌(口腔内細菌)が生息しています。
歯周病菌やむし歯菌のような悪い菌(悪玉菌)だけでなく、有益な菌(善玉菌)、普段は無害で有益な働きもする菌(日和見菌)も存在し、それぞれが互いに影響し合う細菌の世界(口腔内フローラ)を形成しているのです。
口腔内フローラでは、善玉菌、日和見菌、悪玉菌のどれかが増えすぎたり減りすぎたりしても口内環境に悪い影響が出るため、バランスを整えることが重要です。口腔内フローラを整えることで歯周病やむし歯、口臭などの予防ができます。
口腔内フローラを整えるには、規則正しい生活習慣、栄養バランスの確保、ストレスの解消に加え、毎日の歯磨きなどのオーラルケアや、定期的な歯科検診や予防歯科治療(プラーク除去や歯石除去)が重要です。
加えて、専用の歯磨き粉やデンタルリンスなどのアイテムを取り入れるのもよいでしょう。
休息や睡眠をしっかり取る
歯茎の健康には、ストレスや睡眠不足が影響します。体の免疫を整えることが歯茎の炎症の予防につながるので、休息や睡眠をしっかり取りましょう。
歯茎の炎症の多くは細菌感染が原因です。免疫が低下すると細菌への抵抗力が弱まるため、炎症のリスクが高まるのです。
歯茎の炎症の治し方を知った後はセルフケアに一工夫を
歯茎に炎症や違和感、痛みがあると、食事が楽しめないなど、日常生活が損なわれてしまうでしょう。また、歯周病が進行すれば歯を失い、全身疾患を引き起こす可能性もあるのです。
歯茎の健康維持には毎日のオーラルケアが必要ですが、口腔内フローラにも着目するとよいでしょう。
歯肉炎・歯周炎を引き起こす歯周病菌は、歯磨きにより増殖を抑える必要はありますが、ゼロにすることはできません。「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」のバランスを良好に保つことが重要です。
- 合わせて読みたい
- 「口腔内フローラ」を知っていますか?お口の健康が全身の健康に

監修:角田 智之
1992年、明海大学歯学部卒業。日本大学板橋病院、社会保険横浜中央病院、久留米大学病院、(医)高邦会高木病院歯科口腔外科を経て、2008年福岡市博多区につのだ歯科口腔クリニックを開設。2015年同じ博多区内で移転開設し、つのだデンタルケアクリニックに名称変更。予防診療と舌痛症のメンタルカウンセリングを行っている。専門分野は口腔外科、歯科心身症。