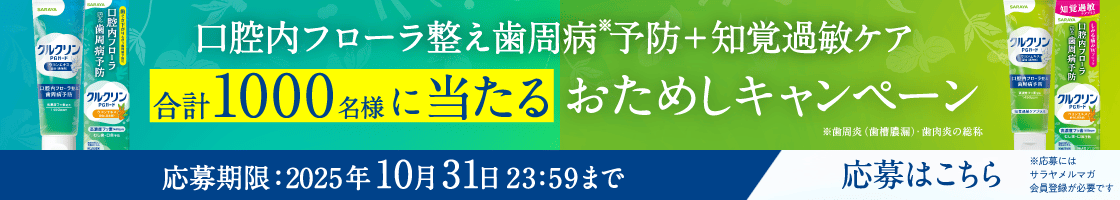女性は口臭がきつくなりやすいって本当?臭いの原因や解消方法

誰しも一度は悩むであろう、自分自身の口臭。日本歯科医師会の調査によると、自分の口臭が気になった経験が「ある」と答えたのは、男性が76.2%、女性が85.3%で、女性の方が自分の口臭を気にするとの結果が出ています(10~70代男女1万人の意識調査、2016年)。
女性のほうが口臭に悩んでいる割合が高いのはなぜでしょうか?一般的に、嗜好品や食生活、生活習慣などの影響から「口臭の強い人は男性が多い」というイメージがあるかもしれません。
この記事では、女性と男性で口臭が強くなりやすいのはどちらか、女性特有の口臭があるのかを解説していきます。
口臭は女性のほうが深刻⁉
口臭が問題になるケースは、男性よりも女性のほうが多いという調査データもあります。
歯科医療機器商社のモリタと口臭測定器メーカーのタイヨウが発表した『口臭白書2019』では、214人の男女(20~60代)の口臭を測定器で計測した結果、13.1%の人に「ニオイを感じる」レベルである「測定値50以上」という結果が出たと紹介されています。
男女別に見ると、基準値にあたる「50以上」の値が出た人は、男性が8.3%なのに対し、女性は17.9%と倍以上の結果が出ています。しかも女性では40代以上の中高年の約4人に1人が「50以上」でした。
『口臭白書2019』では、女性の「口の中の悩み」の5位(回答率26.6%、複数回答可、以下同)は「口臭」との調査結果も示されています。男性の割合(1位、27.9%)よりは低いものの、5人に1人以上の女性が口臭に悩んでいるとの結果です。
このように、口臭が女性にとって大きな悩みであることがわかります。
- 本記事で取り上げる口臭について
- 本記事では、一般的な口臭を取り上げています。
これは専門的には「生理的口臭」と呼ばれるもので、加齢性口臭、起床時口臭(寝起き時の口臭)、空腹時口臭、緊張時口臭、疲労時口臭などが含まれます。
本記事では、歯周病や歯肉炎、口内炎、口腔がんなどの口腔疾患、副鼻腔炎(蓄膿症)、咽頭炎などの耳鼻咽喉科疾患、呼吸器系や消化器系の内臓疾患、糖尿病などの内科系の病気による「病的口臭」、不安障害などの症状による「心理的口臭症」は除外していますのでご注意ください。
病的口臭・心理的口臭症の治療は、専門の診療科への受診が必要です。
また、ニラやニンニク、アルコール、タバコなどの嗜好品や飲食物による一時的な口臭も除外しています。
口臭が発生する仕組み
民間の調査で「女性のほうが男性よりも口臭がある割合が高い」との結果が出たと紹介しましたが、その理由は何でしょうか。まず、口臭の基礎知識を確認したうえで、女性ならでは原因があるのかを解説します。
口臭は、口の中に残った食べカス(食物残渣)や死んだ細胞などのタンパク質を細菌が分解する際に出る臭気物質(ガス)が原因で発生します。
代表的な原因物質は揮発性硫黄化合物(VSC)で、
・卵が腐ったようなにおいのガス(硫化水素)
・野菜が腐ったようなにおいのガス(メチルメルカプタン)
・生ごみのようなにおいのガス(ジメチルサルファイド)
が混ざり合った化合物です。
このように、口臭は口の中に常在する細菌がタンパク質を分解する際に発生するガスが中心であり、「口臭をゼロ」にすることはできないことを覚えておきましょう。口臭の有無というよりは、口臭のレベルに注意することが大切です。
毎日の口腔内ケアを怠りブラッシングが不十分、あるいは不適切になり、食べカスが残ったままになってしまうと、ガスが多く発生して口臭のレベルが高まります。また、唾液分泌量が減って口の中が乾燥する「ドライマウス状態」になると、唾液による殺菌・自浄作用が低下し、細菌が増加して口臭のレベルが高まります。
- 合わせて読みたい
- うがいは口臭に効果がある?臭いの原因や効果的なうがいのやり方
女性の口臭がきつくなる原因
続いて、口臭の高まりに女性特有の要因があるかを解説していきましょう。
女性ホルモン
女性ホルモンと口臭は、密接に関連しています。女性ホルモンとは、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2種類のホルモンのことです。
エストロゲンの分泌は、女性らしい体づくりや生理に欠かせない女性ホルモンに関わります。エストロゲンの分泌が減少すると唾液の量が減り、口腔内の殺菌・自浄作用が低下して口臭が発生しやすくなるのです。
エストロゲンは、初潮を迎える10代から分泌量が増え始め、更年期に減少します。また、生理中も大きく変動し、排卵前に分泌量が急増し、排卵後に急減します。
そのため、ホルモン量が変化する生理前や生理中、妊娠時、更年期には口臭に注意が必要になるのです。
プロゲステロンは、妊娠準備のために働くホルモンで、主に子宮に働き、受精卵が着床しやすい状態に子宮内膜を整えます。プロゲステロンは、炎症を引き起こす物質(プロスタグランジン)を刺激し、歯肉炎を発生させやすくする働きがあります。詳しくは「歯周病」の項目で説明していきます。
ダイエット
食事制限や断食により咀嚼の機会が減ると、唾液の分泌量が低下し、口腔内の細菌が増加して口臭が発生しやすくなります。また、舌の上に付着する細菌のかたまり「舌苔(ぜったい)」が生じやすくなることも口臭の原因になり得ます。
栄養素の偏りも、口臭の発生につながるので注意しましょう。
炭水化物やタンパク質の摂取量が減ると、体内の脂肪がエネルギーとして使われて脂臭(ししゅう)が発生し、口臭につながります。
また、無理な糖質制限を行い、身体が飢餓状態になると、体内のタンパク質や脂肪が分解されます。この際に発生するケトン体は、口臭・体臭のもとです。
ケトン体によるにおいは、特有の「甘ずっぱいような腐ったにおい」で、ケトン臭(飢餓臭)と呼ばれます。
このほか、ダイエットにより基礎代謝量が下がると、乳酸がたまってアンモニア臭がするなど、ダイエットと口臭は密接な関連があると考えられています。
腸内環境
女性に多い慢性的な便秘により腸内環境が乱れると、臭気をもつ有害物質が発生し、それが口臭の原因になります。大腸で吸収された有害物質が血液を巡って肺に達し、呼気を臭くします。ひどい便秘が続く場合は、消化管の中で臭いが逆流していくこともあるでしょう。
また、ストレスやメンタル不調による腸内環境の乱れも有害物質を発生させます。口と胃腸などの消化管は連動しているため、口内環境の悪化にもつながり、口臭を引き起こします。
- 口臭の評価
- 口臭を考えるうえで重要なのは、「第三者が不快に感じるレベルか」、つまり他人の評価や指摘がポイントになるという点でしょう。「口臭が気になる」という自分の精神的な問題であって、実際には口臭が高いレベルに達していないケースも多々あります。
ビニール袋に息を吐いてセルフチェックする方法もありますが客観性に乏しいため、気になるようでしたら市販の検査機器や歯科医院、口腔外科の口臭外来など測定してみるのもよいでしょう。
女性の口臭を改善するには?口の臭いのケア方法
口臭発生のメカニズム、女性ならではの原因がわかったでしょうか。ここでは口臭を軽減・解消する方法を紹介します。普段の日常生活のなかでセルフケアを実践していきましょう。
こまめに水分補給をする
口腔内の乾燥は口臭の原因になるため、こまめに水分補給をして口の中を潤し、乾燥を防ぐことが大切です。1日2~3リットルを目安に水分を摂取しましょう。
水分は、唾液分泌の減少や口腔内細菌の増加につながらないよう、糖分やカフェインの少ないものを選びます。水、あるいは白湯がよいでしょう。
慢性鼻炎などで鼻呼吸ができず、口呼吸になっている方は口腔内が乾燥しやすいので、特に注意してください。唾液腺マッサージなども取り入れて、唾液の分泌を促すとよいでしょう。
定期的に歯磨き・うがいをする
基本の「キ」ですが、歯磨き・うがいは重要な口臭対策です。定期的な歯磨き・うがいにより、歯や歯茎、口の粘膜の健康を保ち、口腔内細菌を減らして食べカスを除去すれば口臭を抑制できます。デンタルフロスや歯間ブラシなども効果的です。
就寝中に口腔内が乾燥することで起床時の口臭が強くなるため(起床時口臭)、就寝前はしっかり歯を磨きましょう。
毎食後の歯磨きも重要です。口臭の多くは、口の中の食べカスを細菌が分解し、臭気物質を発生させることで生じます。また、細菌とその代謝物のかたまりである歯垢(プラーク)も口臭の原因になるため、しっかりと除去しましょう。
歯垢が石灰化して歯磨きで取れないほど硬くなったものを歯石と呼びます。歯石も口臭の原因になるため、定期的に歯医者を受診して除去することが重要です。
食生活を改善する
まず、食べ物をよくかんで食べることが重要です。
咀嚼(咀嚼)には、以下のような効果があります。
①唾液の分泌を促進し、口腔内の殺菌・自浄作用を向上させる
②口の筋肉や歯肉の血行が良くなり、歯肉炎や歯周病の予防になる
③食べ物をかむ摩擦で歯が直接きれいになるなどの働きがあります。
①~③のいずれも重要な口臭対策です。
また、食事が偏ると、「ダイエット」の項で説明した通り口臭の原因になるため、栄養素をバランス良く摂取しましょう。さらに、腸内環境も口臭に関係するため、善玉菌を増やして腸を整える食品を積極的に取ることも大切です。
具体的な食品を表にまとめました。
| 腸を整える食品 | 食材例 |
|---|---|
| 乳酸菌などの善玉菌を含む発酵食品 | ヨーグルト、みそ、納豆、キムチ、チーズ |
| 善玉菌のエサになるオリゴ糖を多く含む食品 | 大豆食品、玉ねぎ、バナナ 、ゴボウ、リンゴ、ハチミツ |
| 便通を整え、善玉菌を増やす食物繊維 | 玄米、もち麦 、そば、キノコ、キャベツ、セロリ 、レタス、ブロッコリー、オクラ 、ゴボウ 、イモ類 、海藻類、イチゴ、かんきつ類 |
ストレスをためない生活を心がける
ストレスがたまると自律神経のバランスが悪化し、唾液の分泌低下を招いて口臭が発生するリスクが高まります。口内炎もできやすくなり、口の中の健康も乱れるため、適度なストレスの発散が重要です。
強い緊張・ストレス状態が続くと、緊張時口臭が発生します。「ダイエット」の項目で説明したのと同じ仕組みでケトン体が生成され、甘ずっぱいケトン臭(アセトン臭)を含んだ口臭になります。
口臭を解消して素敵な毎日を
家事や育児をしながら働く女性も増え、忙しい毎日を送る女性が増えてきました。セルフケアの時間がなかなか取れないなかで、仕事での打ち合わせ、デートなどの場面で口臭を気にする女性も多いことでしょう。
そこで、今回ご紹介した口臭ケアに加えて、歯磨き粉を工夫してみませんか?
口腔内細菌が口臭に大きな影響をもたらすことは、すでに説明した通りです。ただし全ての細菌が悪いわけではありません。善玉菌、日和見菌(有害・無害どちらにも働く菌)、悪玉菌のバランスが良好に保たれていることが重要です。
そうした口腔内の細菌たちが集まる世界=口腔内フローラの視点で開発された歯磨き粉の使用もおすすめです。
- 合わせて読みたい
- 口臭対策におすすめの薬用ハミガキ「クルクリン」について詳しくはこちら

監修:角田 智之
1992年、明海大学歯学部卒業。日本大学板橋病院、社会保険横浜中央病院、久留米大学病院、(医)高邦会高木病院歯科口腔外科を経て、2008年福岡市博多区につのだ歯科口腔クリニックを開設。2015年同じ博多区内で移転開設し、つのだデンタルケアクリニックに名称変更。予防診療と舌痛症のメンタルカウンセリングを行っている。専門分野は口腔外科、歯科心身症。